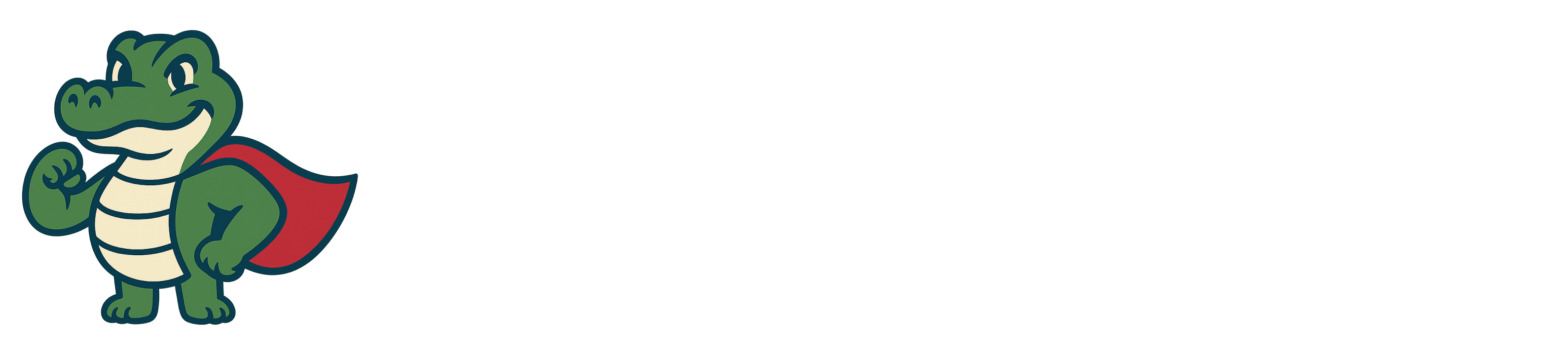以前、あるアパレル企業と関わったときのことです。
その企業は「新規顧客の獲得こそが成長の近道だ」と信じ、広告運用に全力を注いでいました。毎月数百万円単位の予算を投下し、流入を確保することで売上を維持していたのです。
ところが状況は一変します。
広告費が年々高騰し、同時に競合ブランドも続々と参入。かつては安定して流入していた新規顧客数が減少に転じ、売上に直結して落ち込んでいきました。いくら広告を積んでも、以前のような成果が出ない。焦って広告費をさらに上積みしても、利益は薄まる一方でした。
気がつけば、かつては華やかに成長していたブランドが、数年のうちに急速に力を失っていったのです。
この出来事を間近で見て、私は大切なことを学びました。
新規顧客への依存は、広告市場や競合環境に大きく左右される「不安定な成長」しかもたらさないということです。もしその企業が、売上の土台となるリピート基盤を持っていたなら、環境変化にあそこまで振り回されることはなかったでしょう。
新規は入口にすぎず、事業を強くするのはリピートこそが本質なのです。
では、なぜリピートがそこまで大切なのでしょうか。
数字と実例をもとに、その価値を解き明かしていきます。
リピートがなければ、どんな大ヒットも一瞬で終わる
リピートの重要性を象徴する事例として、かつて社会現象となった「ビリーズブートキャンプ」の話があります。
2007年、ダイエット用のDVD「ビリーズブートキャンプ」は爆発的なヒットを記録しました。販売枚数は150万枚、売上は195億円に達し、当時の通販業界を席巻しました。
しかし翌年、売上はわずか9,000万円。200分の1にまで急落しました。なぜでしょうか。
それは、このDVDが「一度買えば終わり」の商品だったからです。確かに中身は素晴らしく、7日間で効果を実感できる内容でした。だからこそ爆発的に売れたのですが、誰も同じDVDを2回、3回と買うことはありません。つまり、リピートが存在しなかったのです。
同じダイエット商品でも、サプリメントや食品であれば状況はまったく違います。顧客が効果を感じれば「また次も買おう」という行動が自然に生まれます。リピート性のある商品は売上が積み上がり、安定した成長が可能になります。
このエピソードが示すのは、どれだけ大ヒットした商品でも、リピートがなければ一瞬で消えてしまうという現実です。売れるかどうか以上に大切なのは、「繰り返し買ってもらえるかどうか」。ビジネスを長期的に続けていくための分かれ道はここにあります。
リピートの価値はどこにあるのか
リピートの大切さは感覚的な話ではなく、数字と実例からも明らかです。
1. コスト効率の圧倒的な差
リピートの価値を最もわかりやすく示すのがコストの違いです。一般的に、新規顧客を1人獲得するコストは、既存顧客にもう一度購入してもらうコストの約5倍かかるといわれています。つまり、同じ売上を作るのであれば、リピーターを増やす方がはるかに効率的です。
さらに、パレートの法則(80:20の法則)を思い出してください。売上の8割は、顧客全体の上位2割の優良顧客=リピーターから生み出されることが多いのです。新規を追い続けるのではなく、リピート率を高めることこそが、売上の最大化に直結します。
そして、リピート率が上がると顧客のLTV(生涯価値)が大きく伸びます。LTVが高まるほど、売上は「毎月ゼロから積み上げる」のではなく「積み上がった基盤の上に加算される」形になります。
リピート強化は、安定的かつ持続的な売上を作る鍵なのです。
2. 経営の安定性
新規依存のストアでは、毎月のスタート地点は売上ゼロです。広告を回さなければ数字が立たず、広告費が高騰したり市場環境が変わったりすると、売上も直ちに影響を受けます。
一方でリピート基盤を持つストアは、翌月の売上がある程度「見えている」状態から始まります。リピートによる売上ベースが積み上がることで、外部要因に振り回されにくく、経営の安定性は格段に高まります。
3. 顧客解像度の変化
リピートは数字の安定性だけでなく、顧客理解の質も変えます。リピーターの声を拾うと、「誰が、なぜ買っているのか」が鮮明になります。
・どのような利用シーンで使われているのか
・何に共感して購入しているのか
・購買を決定づけた要素は何か
こうした顧客の輪郭が明確になることで、商品改善やマーケティング施策の精度が一気に高まります。結果として、新規顧客獲得の効率まで良くなり、成長の好循環を生み出すのです。
リピート率が変わるとブランドはこう変わる
実際にリピートを強化したストアでは、数字と体感の両面で大きな変化が起こります。ここでは、あるブランドの事例を参考にイメージしていただきたいと思います。
このブランドは、当初リピート率が10%程度しかなく、毎月の売上は新規集客に大きく依存していました。広告を止めれば売上も止まる、典型的な新規頼みの構造です。
そこで、顧客体験を見直し、購入後のフォローや継続購入の仕組みを整えることで、リピート率が10%から30%へと改善しました。
その結果、次のような変化が生まれました。
定量的な効果
- 新規獲得数が変わらなくても、売上は約1.5倍に拡大
- 広告費を増やさずに利益率が向上
- リピートによる安定売上が積み上がり、月次の売上予測が可能に
定性的な効果
- ブランドのファンコミュニティが形成され、口コミやSNSでの自発的な拡散が増加
- リピーターの声から商品改善のヒントが得られ、開発サイクルが効率化
- 顧客理解が深まることで、新規向けマーケティングもより精度が高くなり、集客効率まで改善
このように、リピート率がわずかに改善するだけでも、事業全体に広がるインパクトは計り知れません。リピートは単なる売上の追加要素ではなく、利益構造を変え、ブランド価値を高め、成長の土台を築くものなのです。
リピートに関する「よくある誤解」
リピートの大切さを理解していても、実際の現場では誤った認識が根強く存在しています。
誤解1:新規を増やせば自然にリピートはついてくる
多くのEC事業者が抱く典型的な誤解です。新規顧客が増えれば、その中から自然に一定割合がリピートしてくれるだろう、と考えがちです。しかし現実は違います。ほとんどの新規顧客は、初回購入の動機が解消された瞬間に関心を失い、次の購買理由が提示されない限り離脱してしまいます。
例えば月に1,000人の新規顧客を獲得しても、リピート率が10%であれば翌月の再購買者は100人に過ぎません。新規を20%増やして1,200人にしても、リピート率がそのままなら120人しか残らない計算です。逆に、リピート率を10%から20%に改善すれば、新規1,000人のままでも翌月の再購買者は200人になります。新規を増やすよりも、リピート導線を整備した方がはるかに大きな効果を生むのです。
この誤解が生む落とし穴は、購入後の体験設計を怠ることです。商品到着後に価値を再確認させる仕掛けがなく、最適なタイミングで次の購入を促す導線もない。結果として、せっかく獲得した顧客が一度きりで去っていきます。リピートは自然に発生するものではなく、明確に設計された体験から生まれるものだと理解する必要があります。
誤解2:CRMを導入すればリピートは勝手に増える
CRMツールを導入すれば自動的に顧客がリピートしてくれる、というのも大きな誤解です。確かにCRMは顧客データを管理し、メールやLINEなどでコミュニケーションを自動化する便利な仕組みですが、それ自体が戦略を代替することはありません。戦略がなければ、CRMは「一斉配信メールを出す装置」にとどまります。
実際、戦略を持たずにCRMを使うと、配信頻度だけが増えて開封率は下がり、購買行動にはつながらないという状況に陥ります。安易にクーポンをばらまけば短期的な売上は作れますが、利益は削られ、顧客の期待値も歪んでいきます。
本来、CRMの活用には顧客をフェーズごとに分け、それぞれの目的を明確にする設計が必要です。初回顧客には「商品の価値を体験してもらう」こと、2回目顧客には「習慣化を促す」こと、休眠前の顧客には「再度の利用シーンを思い出させる」こと。それぞれ異なる目的に合わせて、適切なタイミングで最適なメッセージを届けることが重要です。
つまり、CRMは戦略を実行するための手段にすぎません。大切なのは「誰に」「いつ」「どんな価値を」届けるかを設計し、そのシナリオを改善し続けることなのです。
誤解3 売上は集客の数で決まる
短期的に見ると、売上は確かに集客数と相関します。だからこそ「とにかく人を集めれば売上が増える」と考えてしまうのですが、利益構造の視点から見ればこれは誤解です。
仮に平均客単価5,000円、粗利率60%だとしましょう。1回の購入から得られる粗利は3,000円です。もし新規顧客の獲得単価が3,000円なら、初回取引で残る利益はゼロ。むしろ梱包費や決済手数料を含めれば赤字になります。では、どこで黒字化するのか。それは2回目以降の購買です。リピートが起これば、広告費をかけずに粗利が積み上がり、初回の投資を回収できます。3回目以降の購買は、ほぼ純粋な利益として積み重なります。
新規集客の数を追うだけでは、広告単価の上昇や競合の影響をもろに受け、事業は不安定になります。しかも新規獲得に最適化された訴求は価格勝負に陥りやすく、ブランド価値を削ってしまう危険性もあります。
正しい捉え方は、「売上は集客数だけでなく、リピート率と顧客単価の掛け算で決まる」という視点です。そして利益を決めるのは、顧客がどれだけ繰り返し買ってくれるかというLTVと、それを獲得するためのコスト(CAC)の差です。リピートを土台に据えてLTVを高めれば、結果的に許容できる獲得コストが広がり、集客施策にも投資しやすくなります。
このように、リピートについての誤解は「自然に起きるもの」「ツールで解決できるもの」「集客で代替できるもの」といった短絡的な考えから生まれています。しかし実際には、リピートは明確な設計と戦略によってこそ実現されるものです。
リピートこそが、成長の分かれ道
ここまで見てきたように、リピートは単なる「追加の売上」ではありません。
第一に、コスト効率の観点です。新規獲得に比べてリピートは圧倒的に低コストで売上を生み出し、LTVを大きく押し上げます。
第二に、経営の安定性の観点です。リピートによる積み上げ型の売上があるからこそ、外部環境や広告費の変動に左右されにくくなります。
第三に、顧客解像度の向上です。リピーターの存在によって「なぜその商品が選ばれているのか」が鮮明になり、商品改善やマーケティングの精度が高まります。これは新規獲得の効率をも引き上げ、成長の好循環を生み出します。
一方で、多くの事業者はいまだに誤解を抱えています。「新規を増やせば自然にリピートが生まれる」「CRMを導入すれば勝手にリピートが増える」「売上は集客数で決まる」。こうした思い込みは、リピートの本質を見誤り、持続的な成長を阻む要因となっています。
だからこそ、リピートは「後から考えるもの」ではありません。
最初から事業の中心に置き、仕組みとして設計することこそ、持続的な成長への最短ルートなのです。
今日から「どうすれば繰り返し買ってもらえるか」を考えてみてください。その一歩が、あなたのブランドを不安定な売上から解放し、長く愛される事業へと導いてくれるはずです。