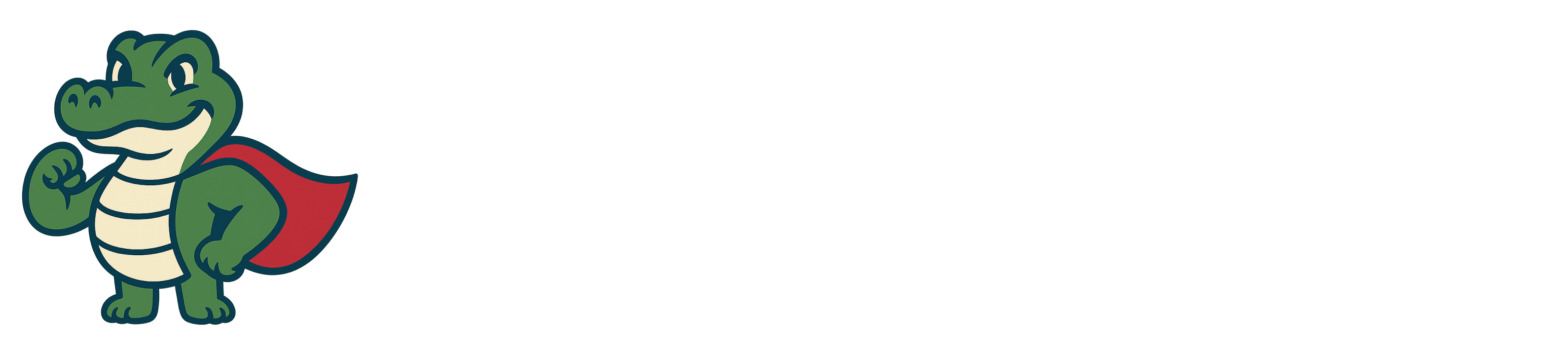「広告を止めた瞬間に、売上も止まるんです。」
支援していたあるサプリメントブランドの担当者からそう打ち明けられたときのことを、今でもよく覚えています。
そのブランドは、1袋3,980円の健康食品を主力商品にしていました。毎月500人以上の新規顧客を集めるために、広告費を300万円以上投下。表面的には「売上は月2,000万円」と順調に見えたのです。
しかし中身を見てみると、新規顧客の約8割は一度きりの購入で終わり。翌月に残るリピート売上は全体の1割にも届きませんでした。つまり、毎月ゼロからのスタート。広告を止めれば売上も消える構造になっていたのです。
担当者は疲弊していました。
「毎月数字は追っているのに、利益はほとんど残らない。広告費は上がる一方で、これ以上どうやって戦えばいいのか…」
そこで切り替えたのが、「リピートを前提に考える」という発想でした。商品設計を見直し、初回購入者に「30日で使い切る量」を届け、20日後に「そろそろ残り少なくなっていませんか?」というフォローを開始。開封ガイドや体験談の冊子を同梱し、継続する理由を丁寧に伝える仕組みを作りました。
結果、リピート率はわずか半年で10%から35%へ。広告費を増やさなくても売上は毎月2,500万円を安定して超え、利益率も改善しました。
新規の数は以前と変わらないのに、売上は安定し、利益が積み上がる。広告に振り回されず、翌月の売上がある程度「見えている」状態になるのです。
そのブランドの担当者は言いました。
「もっと早く、この考え方を知っていれば…」
新規を集めてから考えるのではなく、リピートを前提に設計する。
これこそが、ECの成長を決定づける分かれ道なのです。
では、どうすればいいのか?
多くのEC事業者が悩む課題に対する答えを、誰でも応用可能な形で体系化したのが『リピートファースト戦略』です。
リピートファースト戦略とは何か
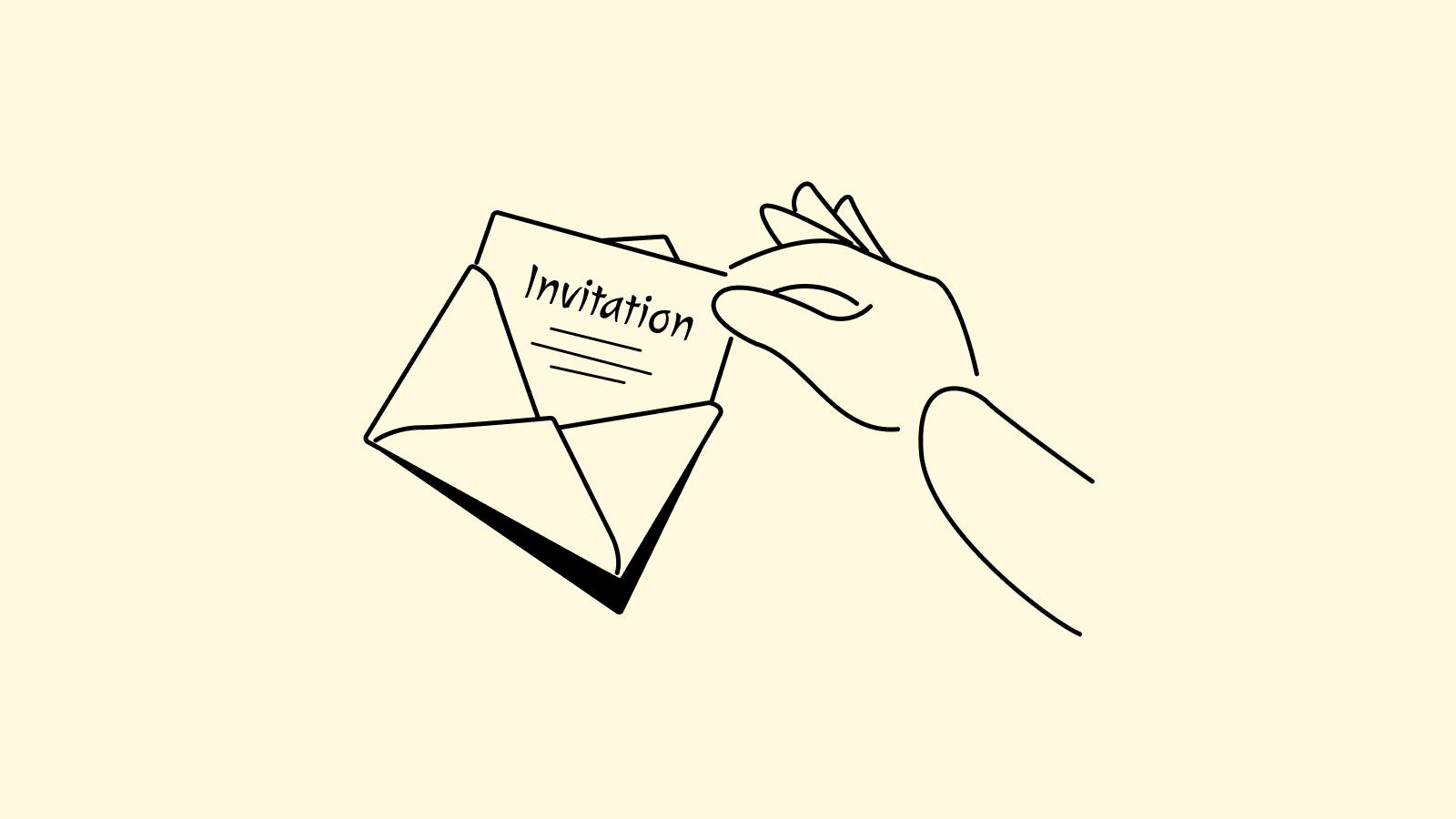
多くのECは「新規を集めてから、リピートを考える」という順番で動いています。
一見、自然な流れに思えますが、この順番こそが利益を削り、広告依存から抜け出せない最大の要因です。
リピートファースト戦略とは、これを根本から逆転させる考え方です。
すなわち「どうすれば繰り返し買ってもらえるか」を最初に設定し、そこから集客や商品設計を逆算していく戦略です。
リピートファーストの基本原則
原則1:LTVを起点にする
売上や新規顧客数ではなく、顧客一人あたりの生涯価値(LTV)を最大化することを目的に据えます。1回の購入での売上ではなく、合計でどれだけの購入をしてもらえるのかを基準に考えます。
原則2:初回購入からリピート導線を設計する
最初の購入から次につながる仕掛けを組み込みます。お試しセットから定期便への誘導や、同梱物・フォローメールで体験を整えることで、自然に「また買おう」と思える流れをつくります。
原則3:顧客理解を継続する
データや顧客の声を通じて「なぜ選ばれているのか」を明らかにし、施策に反映します。顧客解像度が高まることで、商品の改善や広告の精度も上がり、新規獲得にも良い影響が生まれます。
なぜリピートファーストが大切なのか
利益構造が変わる
新規獲得はリピート獲得よりも約5倍のコストがかかります。初回で利益が出なくても、2回目以降は広告費ゼロで粗利が積み上がるため、黒字が継続的に増えていきます。
経営が安定する
新規依存では毎月ゼロからのスタートですが、リピート基盤があれば翌月の売上がある程度見えている状態から始められます。これにより、売上予測や在庫計画、資金繰りが安定します。
集客が楽になる
LTVが高まれば、許容できる獲得単価(CAC)が広がります。その結果、競合よりも有利に広告を運用でき、より良質な新規顧客を集めやすくなります。
ブランドが強くなる
リピーターはファン化し、SNSや口コミで商品を広めてくれます。顧客の声を商品や体験改善に活かすことでブランド自体も磨かれ、長期的に選ばれ続ける存在になります。
つまり、リピートファースト戦略とは 「リピートを偶然ではなく必然にする仕組み」 を作ることなのです。
リピートファースト戦略の3つの柱
リピートファースト戦略を実際に形にしていくには、商品設計・購入後体験・データ分析 の3つを柱に据えることが大切です。ここからは、それぞれで実際に何をすべきかを詳しく見ていきます。
① 商品設計
リピートの有無は、商品そのものの設計に大きく左右されます。いくら顧客接点やCRMを工夫しても、商品がリピートに向かない構造なら成果は限られてしまいます。そこで、商品を「どう繰り返し買ってもらえるか」という視点で再設計します。
入口商品を用意する
新規顧客が最初に手に取りやすい低価格・低リスクの商品を用意します。例えば、スキンケアならトライアルセット、食品なら小容量パック。まずは「買ってもらう」ハードルを下げることが重要です。
リピート商品を設計する
使えばなくなる、習慣的に消費される、買い替えのタイミングが明確、といった性質を持つ商品を主力に据えます。これにより、顧客が自然に「また必要だから買う」という行動をとりやすくなります。
商品ポートフォリオを流れで考える
単品で終わるのではなく、「入口商品 → 主力商品 → 定期便やまとめ買い → 高単価商品」というように、顧客の購買体験をストーリー化します。顧客が自然に次のステップへ進めるように設計することで、LTVが飛躍的に伸びます。
推奨Shopifyアプリ:
定期購買 / Go Sub / かんたんサブスク(定期購買)
Shopify Bundles / シンプルセット販売 / Fast Bundle(セット販売)
② 購入後体験・顧客接点
「最初に買ってもらった」顧客を、いかにして次の購買につなげるか。そのカギは購入後体験にあります。顧客は商品が届いた瞬間から、リピートするか離脱するかを決め始めています。
到着後の感動体験
箱を開けたときのワクワク感は、記憶に強く残ります。ブランドの世界観を伝えるパッケージ、ちょっとしたサプライズやブランドストーリーの同梱物は「また買いたい」と思わせるきっかけになります。
使い方・価値を伝える
購入した商品をどう使えば効果的かを、わかりやすく伝えることで満足度は格段に上がります。使い方ガイドや動画、体験談を届けることで、「続ける理由」が顧客の中で強化されます。
リマインド導線を設計する
商品の利用サイクルに合わせて、自然なタイミングでフォローを入れます。例えば「20日後に補充リマインド」「30日後に定期コースの提案」といった流れをあらかじめ設計しておくことで、リピート率が大きく改善します。
ファン化を促す仕組み
レビューやSNS投稿の依頼、ポイント制度、会員ランクなどの仕組みを取り入れることで、顧客は「単なる購入者」から「応援者・ファン」へと変化します。ファン化が進むと口コミや紹介が自然に生まれ、新規獲得にもつながります。
推奨Shopifyアプリ:
Shopifyメール / Klaviyo / CRM PLUS on LINE(メール・LINE)
Yotpo / Judge.me(レビュー)
Smile.io / VIP / Joy(ロイヤリティ)
③ データ分析・顧客理解
最後に重要なのが、データをもとに「誰が、なぜ買っているのか」を理解し続けることです。リピート率やLTVはもちろん、顧客の声や感情を分析して、次の施策に活かします。
定量データの活用
リピート率(全体・初回→2回目)、購入間隔、コホート別LTV、休眠率といった指標を追うことで、リピートの全体像を把握します。例えば「初回→2回目の転換率が15%しかない」とわかれば、そこを改善する施策に集中できます。
定性データの収集
購入後アンケートやインタビュー、レビュー分析を通じて「なぜ買ったのか」「どんな場面で使っているのか」「何に満足しているか/不満があるか」を把握します。数字だけでは見えない「顧客の解像度」がここで明らかになります。
セグメントごとの施策
初回顧客、2回目顧客、優良顧客、休眠顧客とフェーズごとに分け、それぞれに適切なアプローチを行います。例えば、休眠前の兆候が見える顧客には「特別なクーポン」を届け、優良顧客には「VIP体験」を用意するといった施策です。
改善サイクルを回す
データをもとに仮説を立て、施策を試し、結果を測定し、また改善する。このサイクルを継続的に回すことで、リピート施策は徐々に精度を増していきます。
推奨Shopifyアプリ:
ECPower / Lifetimely / Peel(LTV分析・コホート分析)
Asklayer / Fairing(購入後アンケート)
この3つの柱を同時に回すことで、リピートは「偶然の結果」ではなく「必然の仕組み」として生まれるようになります。
リピートファースト戦略を実践したストアの変化
リピートファースト戦略を導入したあるコスメブランドの事例をご紹介します。
導入前:新規依存で苦しい日々
このブランドは、主力商品を1本3,500円の美容液に設定し、広告に毎月300万円以上を投下していました。新規顧客は毎月500人以上獲得できており、表面的な売上は月2,000万円を超えていました。
しかし、実際の利益はほとんど残りません。なぜなら、新規獲得のコストが1人あたり3,000円を超えていたからです。初回の粗利は広告費で消え、2回目以降の購入がなければ黒字が積み上がらない構造でした。にもかかわらず、リピート率はわずか10%程度。大半の顧客は一度きりで離脱していたのです。
経営者は「毎月ゼロからのスタートラインに立たされている気分だ」と語っていました。広告を止めれば売上も止まる、不安定で消耗の大きい経営が続いていたのです。
転機:リピートを前提に設計する
この状況を打開するために、リピートファースト戦略を導入しました。ポイントは「どうすれば繰り返し買ってもらえるか」を最初に設計し、そこから商品や施策を逆算することでした。
まずはLTVを起点に意思決定することを徹底しました。新規数や広告効率ではなく、「初回→2回目→3回目」の残存率を追い、2回目で投資を回収するシナリオをKPIに設定しました。
次に、初回購入からリピート導線を組み込む取り組みを始めました。
-
入口商品として、初回限定のトライアルセットを新設
-
商品に「30日で使い切る量」を設定し、自然に次の購入タイミングが生まれるように設計
-
開封時にブランドの世界観や使い方を伝える冊子を同梱
-
到着7日後にHow To動画メール、20日後に補充リマインド、30日後に定期コース提案を配信
さらに、顧客理解を継続する仕組みも整えました。
-
購入後アンケートで「なぜ買ったのか」「どんな場面で使っているか」を収集
-
レビュー分析で顧客が実際に使う言葉を抽出し、広告コピーや商品説明に反映
-
データではリピート率やリオーダー間隔を常に追い、コホート分析で顧客の残存率を把握
このように「商品設計」「購入後体験」「データ分析」の三つの柱を同時に強化したのです。
導入後:安定と成長の好循環へ
導入から半年後、リピート率は10%から35%へ改善しました。新規獲得数が大きく変わらないにもかかわらず、月商は2,500万円を安定的に超えるようになり、利益率も大幅に改善しました。
LTVが伸びたことで許容できる獲得単価(CAC)が広がり、広告運用の自由度も高まりました。結果として新規獲得の効率まで改善し、新規とリピートの「好循環」が回り始めたのです。
さらに、顧客理解が深まったことでブランドメッセージが明確になり、SNSや口コミで自然な広がりも生まれました。レビューやUGCが増え、広告以外の流入チャネルが育った結果、新規顧客の獲得コストも下がっていきました。
この事例が示すように、リピートファースト戦略は単なる施策の寄せ集めではありません。
「リピートを偶然に任せるのではなく、必然として生み出す仕組みを最初から設計する」ことによって、利益構造が変わり、経営が安定し、ブランドが強くなります。
リピートファースト戦略のまとめ

ECの世界では、多くの事業者が「新規をどれだけ集められるか」に追われています。けれど、本当に強いブランドは違います。「どれだけ繰り返し買ってもらえるか」こそが、成長を決定づける要因なのです。
リピートファースト戦略は、難しい理論ではありません。LTVを軸に考え、初回から次につながる仕掛けを整え、顧客理解を深め続ける。それだけで、売上の形は大きく変わっていきます。
新規依存から抜け出したとき、あなたのストアには毎月積み上がる売上が生まれ、経営は安定します。広告費に振り回される日々から解放され、顧客と向き合う時間が増え、ブランドを育てる楽しさを実感できるはずです。
そして何より、リピート顧客がファンになり、自然に口コミや紹介が広がっていく。その瞬間、事業は「追いかける成長」から「引き寄せる成長」に変わります。
リピートは偶然ではありません。設計すれば必ず生まれるものです。
今日から「リピートを前提に考える」ことを始めてみてください。小さな一歩が、長期的な成長への大きな一歩につながります。