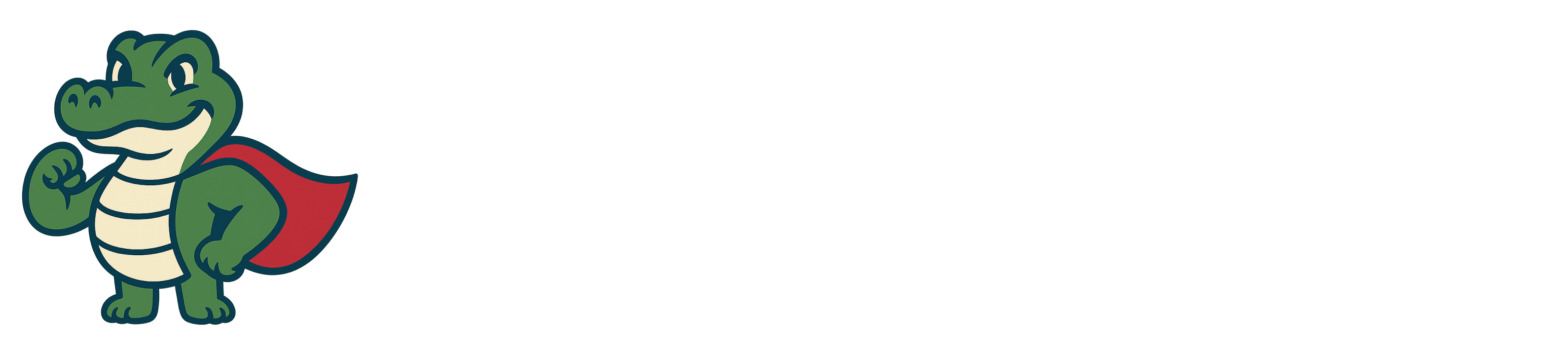「広告費をかけてもリピートが増えない」
「新規顧客は伸びているのに、LTVが頭打ちになる」
「CRMやLINEを導入したけど、成果につながらない」
これは、私が50社以上のECを支援してきた中で、最も多く聞く悩みです。
EC運営は、商品開発・在庫管理・フルフィルメント・広告運用と、まさに"総合格闘技"。やるべきことが多すぎて、マーケティングやデータ分析に手が回らない事業者も少なくありません。
しかし、数百社を支援してわかったのは「分析の仕方」ひとつで、売上は劇的に変わるという事実です。
よくある誤解:「How」から入ってしまう
多くの事業者は、売上を伸ばそうとするときに「手段=How」から入ってしまいます。
- とりあえずCRMを導入する
- LINE公式アカウントを始めてみる
- メルマガや広告運用に力を入れる
こうした施策自体は間違っていません。ですが、「誰に届けるのか」「なぜそれが必要なのか」が不明確なまま進めると、結局うまくいかないケースが大半です。
実際、あるアパレルECではメルマガを導入したものの、「誰に」「どんな理由で」配信するかを考えずに一斉配信を続けた結果、半年後には開封率が10%以下に低迷してしまいました。
一方、成功した例もあります。あるコスメECでは、施策を打つ前に顧客データを徹底的に分析しました。
すると、「2回購入したが3ヶ月以上購入していない顧客」が全体の23%を占めており、この層のLTVポテンシャルが非常に高いことが判明。そこで、この層だけに特化した「お帰りなさいキャンペーン」を実施したところ、3ヶ月で売上が前年同期比で127%に成長しました。
この差は何か?それは「誰に届けるか」を明確にしていたかどうかです。
分析の本質は「顧客を理解すること」
ビジネスは"誰か"を喜ばせることで成り立ちます。それは、たとえばプレゼント選びにも似ています。
「何を贈ればいい?」と聞かれて、いきなり「花束がいいよ」と答える人はいません。まず、「誰にあげるの?」と聞くはずです。
ECもまったく同じ。相手(顧客)を知らずに施策だけを打っても、当たるかどうかは"博打"です。
だからこそ、データ分析の本質は「顧客理解」にあります。顧客の行動を見て、分けて、理解して、初めて意味のある施策が打てるのです。
データ分析とは「分けて見る」こと
そもそも、分析とは何か?
「知りたいことに対して、分けて、比較して、気づきを得ること」
これが分析の定義です。
たとえば、分けることによってこのようなことが分かります。
- 月別に売上を見れば、季節性がわかる
- 商品別に見ると、売れ筋が見える
- 流入元で分けると、広告の効果が見える
重要なのは、「分けて見る」ことです。そして、分ける軸として5W1Hを活用することをオススメします。
- When(いつ):購入日、曜日、時間帯、月別など
- Where(どこから):流入元、広告チャネル、SNS、店舗など
- What(何を):商品、カテゴリ、セット、クーポンなど
- Who(誰が):新規/リピーター、購買回数、LTV別、地域別など
- How much(いくら):購入金額、平均単価、カート単価など
- How(どうやって):決済手段、配送方法、注文経路、注文タグなど
実際の分析の流れ
「売上が落ちている」「思ったようにLTVが伸びない」そう感じたときに、どのような角度でデータを見ればよいか。実際の分析の切り口を紹介します。
When(いつ)
- 月別で売上を比較してみる
- 曜日別・時間帯別に売上や購入件数を見てみる
- キャンペーン期間前後で売上・CVRに差があるかを比較する
- 季節性・繁忙期のパターンを探る
【実例】
ある食品ECでは、時間帯別に分析したところ、夜21時〜23時の購入が全体の38%を占めていることが判明。この時間帯に合わせてLINE配信を実施したことで、開封率が従来の2.3倍に向上しました。また、「初回購入から2週間後」のタイミングでフォローメールを送ると、リピート率が1.7倍になることもわかりました。
Where(どこから)
- 広告チャネル別(Google, Meta, LINEなど)でCVRやLTVを見る
- UTMパラメータでキャンペーンごとの売上貢献を比較
- 店舗ごとの販売状況を比較(オンラインvs.実店舗など)
- 初回購入の流入元ごとにリピート率を比較する
【実例】
あるアパレルECでは、流入元別のLTVを分析したところ、Instagram経由の顧客はCPAが高いものの、6ヶ月後のLTVは他チャネルの1.8倍だったことが判明。一方、Google広告経由は初回購入率は高いが、リピート率が低い傾向がありました。この分析により、「Instagramは長期的な顧客育成に投資」「Googleは短期売上のため」と広告戦略を最適化し、ROASが35%改善しました。
What(何を)
- 商品別・カテゴリ別に売上や平均単価を比較
- クーポンごとの使用回数や利用者の傾向を比較
- セット商品 vs 単品購入でLTVの違いを見る
- 売れ筋商品を買った人が次に買った商品を分析する
【実例】
ある化粧品ECでは、初回購入商品別にその後のリピート率を分析。すると、「スキンケアセット」を初回購入した顧客は、単品購入者に比べて3ヶ月以内のリピート率が2.4倍高いことがわかりました。また、「美容液Aを購入した人の68%が次に化粧水Bを購入する」というクロスセルパターンも発見。この知見をもとに、商品ページや購入後メールでレコメンドを最適化し、客単価が22%向上しました。
Who(誰が)
- 新規 vs リピーターで平均注文金額を比較
- LTVが高い顧客の特徴(購入商品・流入元など)を探る
- 「3回以上購入した顧客」の行動を深掘りする
- 都道府県や国別で売れ筋やリピート率の違いを確認する
【実例】
ある雑貨ECでは、上位20%の優良顧客を分析したところ、3つの共通点が見つかりました:①初回購入金額が平均より30%高い、②初回購入から30日以内に2回目の購入をしている、③Instagram経由での購入が多い。この特徴をもとに「初回高単価購入者」に特化した30日間フォローアップ施策を実施。結果、該当セグメントのリピート率が42%から67%に向上し、年間LTVが1.9倍になりました。
How much(いくら)
- 商品別・チャネル別の平均購入金額を比較
- 施策前後で顧客あたりの購入単価の変化を見る
- 高単価商品の販売比率の推移を確認する
- 一人当たりの平均月間売上(MRR的指標)を算出する
【実例】
ある食品ECでは、購入金額を3つの層(3,000円未満/3,000〜7,000円/7,000円以上)に分けて分析。すると、初回購入金額が7,000円以上の顧客層は、わずか全体の15%ながら、6ヶ月後の売上の48%を占めていることが判明。そこで「初回7,000円以上で送料無料+特典」という施策を導入したところ、高単価顧客の獲得数が2.1倍に増加し、全体の売上が34%向上しました。
How(どうやって)
- 支払い方法別(クレカ、後払いなど)にCVRを比較
- 注文タグで分析して、特定キャンペーン参加者のLTVを見る
- 配送方法別のキャンセル率や再購入率を見る
- サブスク注文者と単発注文者の継続率を比較する
【実例】
あるコスメECでは、決済方法別のデータを分析したところ、後払い決済を選択する顧客のキャンセル率が15%と高い一方で、クレジットカード決済の顧客はリピート率が1.5倍高いことが判明。また、定期購入(サブスク)を選んだ顧客の12ヶ月継続率は78%で、LTVは単発購入の3.2倍でした。この分析から、「初回購入時に定期購入を提案する動線」を強化し、定期購入率が18%から29%に向上しました。
「誰」を主語にするセグメント思考
ここで重要なのが、「セグメント」の視点です。
データを分けるとき、つい「商品」や「施策」を主語にしてしまいがちですが、本質はその裏にいる「人=顧客」です。
- 「この商品が売れている」→「この商品を買った人はどんな人か?」
- 「このクーポンが使われた」→「このクーポンを使ったのはどんな人か?」
商品や施策は手段にすぎません。本当に知りたいのは、"どんな人"が、どんな行動をしているのか。
この"〜な人たち"で分けることが、「セグメント」です。セグメントごとの行動を理解することで、やるべき打ち手は自然と見えてきます。
実践的なセグメント分析の例
実際にどのようなセグメントで分けると効果的か、具体例を紹介します。
【購買行動によるセグメント】
- 新規顧客(初回購入のみ)
- 継続顧客(2回以上購入)
- 休眠顧客(3ヶ月以上未購入)
- VIP顧客(LTV上位20%)
- 離脱リスク顧客(以前は頻繁に購入していたが最近減少)
【購買頻度×金額のRFM分析】
- Recency(最終購入日):最近購入したか
- Frequency(購買頻度):どのくらいの頻度で購入しているか
- Monetary(購買金額):累計いくら購入しているか
この3つの軸で顧客を9〜27セグメントに分類し、それぞれに最適な施策を打つことで、限られたリソースで最大の効果を出せます。
【実践例】あるアパレルECのセグメント別施策
このECでは、顧客を5つのセグメントに分類し、それぞれ異なるアプローチを実施しました:
① 新規顧客(購入1回):初回購入から14日後に「2回目購入で使える15%OFFクーポン」を配信 → リピート率が28%向上
② アクティブ顧客(直近3ヶ月で2回以上購入):新商品の先行案内や限定セールを優先配信 → 購買頻度が1.4倍に
③ 休眠顧客(3〜6ヶ月未購入):「お久しぶりです」メッセージと特別オファー → 15%が再購入
④ VIP顧客(LTV上位20%):専用のサンクスレターと次回使える1,000円クーポン → 年間購入回数が4.2回から6.1回に増加
⑤ 離脱リスク顧客(以前は月1回購入だったが、最近2ヶ月未購入):パーソナライズされた商品提案とアンケート → 30%が再購入し、フィードバックも獲得
結果、全体のリピート率が34%から51%に向上し、年間売上が1.8倍になりました。
データ分析でよくある3つの失敗パターン
ここで、多くのEC事業者が陥りがちな失敗パターンと、その解決策を紹介します。
【失敗①】データを見ても「で、何をすればいいの?」となる
よくあるのが、「売上レポートを眺めているだけ」という状態です。数字は見ているが、そこから何をすべきかがわからない。
【解決策】分析の目的を明確にする
まず「何を知りたいのか?」を決めましょう。
- リピート率を上げたい → 「2回目購入した人」と「1回のみの人」を比較する
- 広告効果を改善したい → チャネル別のCPAとLTVを比較する
- 売上を伸ばしたい → どのセグメントが最も伸びしろがあるか分析する
目的がないデータは、ただの数字の羅列です。
【失敗②】全体の平均値だけを見て判断してしまう
「平均購入金額は5,000円」という情報だけでは、実態は見えません。
たとえば、以下の2パターンは平均5,000円でも、まったく違います。
- パターンA:ほとんどの顧客が4,500〜5,500円を購入
- パターンB:3,000円の顧客が70%、15,000円の顧客が30%
平均値は、極端な値に引っ張られやすく、実態を隠してしまうことがあります。
【解決策】分布を見る、セグメントで分ける
平均だけでなく、中央値や分布、セグメント別の数値を見ましょう。パターンBのような状況なら、「高単価顧客をどう増やすか」「低単価層にアップセルできないか」といった具体的な施策が見えてきます。
【失敗③】分析して満足してしまう(施策につなげない)
「面白い傾向が見つかった!」で終わってしまうケースも多いです。分析は、あくまで手段であり、目的ではありません。
【解決策】分析→仮説→施策→検証のサイクルを回す
たとえば、「Instagram経由の顧客はLTVが高い」という分析結果が出たとします。
- 仮説を立てる:「Instagram経由の顧客は、ブランドへの共感が強いからリピートしやすいのでは?」
- 施策を打つ:Instagramへの広告投資を増やす、Instagram限定キャンペーンを実施
-
検証する:3ヶ月後にLTVやROASを測定し、仮説が正しかったか確認
このサイクルを回すことで、データが売上に直結します。
今日から始められる!実践的な3ステップ
「分析が大事なのはわかったけど、何から始めればいいの?」という方のために、今日から実践できる具体的なステップを紹介します。
【ステップ1】まずは新規とリピーターを分けて見る(所要時間:15分)
最もシンプルで効果的な分析は、「新規顧客」と「リピーター」で売上を分けることです。
Shopifyであれば、管理画面の「分析」→「売上レポート」から、顧客タイプ別の売上を確認できます。
確認すべきポイント:
- 新規とリピーターの売上比率は?(理想は新規40%、リピート60%)
- リピーターの平均注文金額は新規の何倍?(通常1.5〜2倍が目安)
- 月ごとの推移で、リピート売上は伸びているか?
この数字を見るだけで、「新規獲得に依存しすぎている」「リピート施策が機能していない」といった課題が見えてきます。
【ステップ2】ロイヤル顧客の特徴を3つ書き出す(所要時間:30分)
次に、「LTVが高い顧客」や「3回以上購入している顧客」の特徴を探りましょう。
見るべきポイント:
- 初回購入した商品は何か?
- どの流入元(広告チャネル)から来たか?
- 初回購入金額はいくらか?
- 初回購入から2回目購入までの期間は?
たとえば、「初回にセット商品を買った人」「Instagram経由の人」「初回7,000円以上購入した人」がリピートしやすいとわかれば、その層を増やす施策を打てばいいのです。
【ステップ3】1つのセグメントに施策を試す(所要時間:1週間)
分析で見えた気づきをもとに、小さく施策を試してみましょう。
例:
- 「初回購入から2週間後にリピート率が高い」→ 2週間後にクーポン付きメールを配信
- 「セット商品購入者のLTVが高い」→ 商品ページでセット商品を目立たせる
- 「3ヶ月未購入の休眠顧客が多い」→ 特別オファーで再購入を促す
重要なのは、全員に同じことをするのではなく、「特定のセグメント」に絞って施策を打つことです。
そして、1ヶ月後に効果を測定し、うまくいったら横展開、うまくいかなければ別の仮説を試す。このサイクルを回すことで、確実に成果が積み上がっていきます。
まとめ:EC分析は顧客を理解するための視点
データ分析の本当の目的は、ただ施策を打つことではなく、顧客を深く理解することにあります。
本記事で紹介した内容をまとめると:
✓ 分析の本質は「顧客を理解すること」
✓ 5W1Hで「分けて見る」ことで、気づきが生まれる
✓ 主語は常に「どんな人たち」か(セグメント思考)
✓ 平均値だけでなく、分布やセグメント別に見る
✓ 分析→仮説→施策→検証のサイクルを回す
✓ まずは新規とリピーターを分けることから始める
数字を「分けて見る」ことで、売上が伸び悩む原因や改善のヒントが見えてきます。そして、そのときに主語になるべきは商品や施策ではなく、"どんな人たち"がどんな行動をしているのか、という顧客の姿です。
つまり、ECの成長を左右するのは顧客理解の深さです。
---
今、あなたのECには必ず「売上を伸ばすヒント」が眠っています。それは、すでに蓄積されているデータの中にあります。
今日できる一歩として、ぜひこの記事を閉じたら、すぐに管理画面を開いて、先月の売上を「新規」と「リピーター」で分けてみてください。その違いを知ることこそ、次に打つべき施策を考えるための最大のヒントになるはずです。
「データを見る」のではなく、「顧客を理解する」。この視点の転換が、あなたのECを次のステージに導きます。